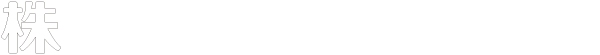田中角栄が1972年に打ち出した「日本列島改造論」は、交通・情報の全国ネットワーク整備を通じて東京一極集中の是正と地方分散を目指す大規模な国土構想でした。掲げられた構想のうち、現在までに実現したもの、途中で凍結・変更されたもの、そして現代政策へ受け継がれた要素を整理します。
出典:ウィキペディア
1. 列島改造の主要な骨子(要点)
2. 実現したこと:インフラ網の拡充(進捗は高い分野)
田中の提言は長期的にはインフラ整備の方向性を決め、北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線などの整備新幹線や全国の高速道路網の拡充は、その流れを汲むものとして実現・継続しています。とくに地方の主要幹線整備や新幹線ルートの一部は「列島改造論」で示された案が下地になっていると言えます。西九州新幹線などは、基本計画が公示されてから数十年を経て実現に至った例です。
出典:日経BizGate
3. 凍結・挫折した面(進捗が遅れた/実現できなかった分野)
一方で、1970年代のオイルショックやインフレにより、列島改造に伴う大型投資は一時凍結されました。急速な全国開発は土地バブルや物価上昇を生み出し、経済情勢に応じて政策の優先順位が変わったため、当初の構想どおり全面的に実現したわけではありません。多くの都市開発プランや地域特区のような構想は縮小・見直しが余儀なくされました。
出典:日経BizGate
4. 結果としての地域格差と“平準化”の副作用
高速道路や新幹線で結ばれることで、移動・物流は確かに便利になりましたが、一方で「どこへ行っても同じ風景」になった、地域固有の産業や観光資源の魅力が薄れた、といった批判もあります。つまり、ハード面での平準化は進んだものの、地域ごとの経済活力や自律的な成長を必ずしももたらさなかった面も指摘されています。現代の地方創生では、ハード整備とともにソフト(産業振興・人材育成・地域ブランド化)の両輪が重視されるのはこの反省の延長線上にあります。
出典:シノドス
5. 現代政策との接続:列島改造の「遺産」と教訓
今日の「地方創生」施策や地方交付税、地域再生プランにおいて、列島改造論の発想(交通ネットワークを起点とした地域振興や国による投資の重要性)は継承されています。ただし、実施手法は変化しました。以前のような一律の土木投資中心ではなく、地域ニーズ・強みを生かす選択的投資、民間活力の導入、長期的な人口動態を踏まえた戦略が求められています。過去の過剰投資や短期的景気刺激のリスクを避けるための「ガバナンス」と「コスト効率」の視点が強まっています。
出典:シノドス
6. 現在の進捗度合い(総括)
| 区分 | 内容 | 進捗度 |
|---|---|---|
| 完成・進行中 | ・新幹線整備(複数路線) ・高速道路網 ・主要ダム | 高 |
| 実行中・計画進行中 | ・港湾改良 | 高 |
| 部分的実現 | 一部の都市開発や産業再配置は達成されるも、地域経済自立には課題が残る | 中 |
| 未達・凍結 | 当初想定の大規模投資全体の恒常化や短期間での全国同時活性化は実現せず。政策変更や財政・物価ショックで縮小した部分が多い。 | 低 |
8. 結び
田中角栄の「日本列島改造論」は、すべてが完成したわけではありませんが、現代のインフラ整備と地方政策に大きな影響を与えました。次に問いたいのは、「今後の地方創生において、ハード整備とソフト施策の最適な配分はどうあるべきか?」という点です。読者の皆さんは、あなたの地域でどの施策が最優先だと感じますか?